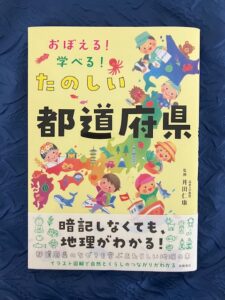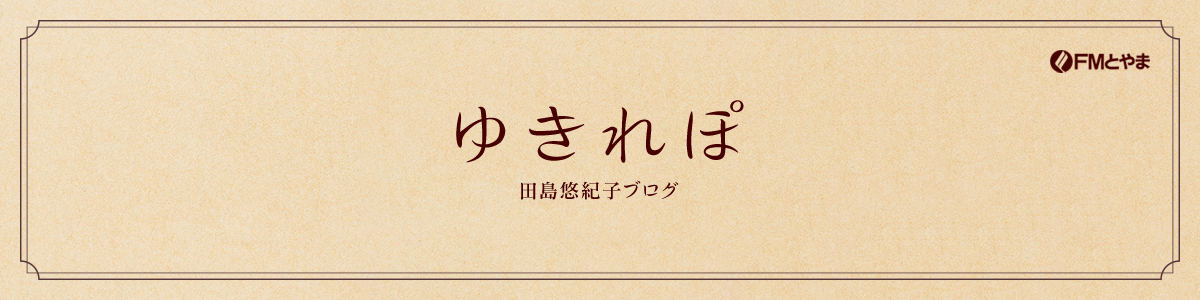
2025年4月23日
- #本
- NEW
『おぼえる!学べる! たのしい都道府県』
もうすぐゴールデンウィークです。
今年はどのように過ごす予定ですか?
今日は行楽の季節に家族みんなで楽しめる本をご紹介します。
『おぼえる!学べる! たのしい都道府県』
井田仁康(いだ・よしやす)監修
高橋書店
本を監修された井田さんは、地理教育・社会科教育学がご専門の筑波大学の教授で、
これまでたくさんの地理関連の児童書や学習参考書などを監修されているそうです。
この本はタイトルの通り、都道府県について学べる一冊です。
本の帯には「都道府県のなぜ?を学ぶあたらしい地理の本」とあります。
主な対象読者は小学3~6年生とその保護者だそうです。
小学生を対象にしているため、漢字にはふりがながふられ、難しい表現も使われていません。
イラストも多いので、マンガを読んでいる感覚で楽しめます。
今の日本はどこに行っても同じようなお店が並んでいて、
それほど違いは無いように感じられますが、
この本を読むと、日本は土地によって気候や地形がかなり異なっていることに気付かされます。
そして、それぞれの土地で、その土地に合わせて暮らす中で、
その土地ならではの特徴や文化が生まれていったことがわかります。
本の構成は、まずはざっくり日本とはどんな場所なのかの説明から始まり、
その後は関東、中部といった地方ごとの特徴、そして各都道府県の特色へと続いていきます。
各都道府県の紹介ページでは、
その都道府県の何がすごいのかが3つにしぼって紹介されているほか、
「なぜこれが有名なの?」「どうしてこうなったの?」といった
気になる疑問がQ&Aの形で紹介されています。
たとえば、
・なぜ青森でりんごが有名なの?
・なぜ香川はうどん県になったの?
・なぜ大阪でお笑い文化が生まれたの?
などです。
これらの理由わかりますか?
りんごとうどんは気候が関係しているのですが、お笑い文化はちょっと違います。
大阪は「天下の台所」と呼ばれる商業のまちとして栄えましたよね?
ものを売る商人たちがお客さんたちとコミュニケーションをとる中で
言葉のやり取りを楽しむようになり、お笑い文化に繋がっていったと言われているのだとか。
この「なぜ?どうして?」に関しては、
その理由がイラスト共にわかりやすく解説されているのもポイントです。
それから「各都道府県のあるある」も面白かったです。
たとえば、
・茨城県は「いばらぎ」じゃなくて「いばらき」。
・千葉県は学校の出席番号は、あいうえお順ではなく誕生日順。
・神戸市の小中学校は、ほとんどが土足で上ばきを履かない。
こんな感じで子どもたちにとっても身近な話題が多めです。
この本は「なぜ?」「どうして?」と考えながら学べるので、
考える力もついて、さらにしっかり覚えることができるように思いました。
ぜひ今年のゴールデンウィークに、ご家族みんなでお読みになってみてはいかがでしょう。
楽しんで読んでいるうちに日本の自然、文化、産業について学べてしまうなんて、
なんか得した気分になりませんか?(笑)
大人の皆さんは、日本の地理の学び直しにもおすすめです。
私は「へぇ、知らなかった!」というものも結構あって勉強になりました。
たとえば愛媛の今治タオルは、5秒で完全に水を吸えないと今治タオルを名乗れないのだとか。
知らなかったー!
-
プロフィール

田島 悠紀子
Tajima Yukiko
7月13日生まれ。群馬県出身。
B型。 -
担当番組
・富山ダイハツ オッケイウィークエンド
(毎週土曜 11:00~11:55)・ヨリミチトソラ
(毎週水曜・木曜 16:20~19:00) -
最新の記事
-
テーマ
-
月別
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年